Junk Onishi『Tea Time』
 | Tea Times(SACD HYBRID) 3,100円 Amazon |
大西順子の何度か目( kumc の記憶では2回?)の引退後の復帰作です。
kumac は、大西順子の演奏は好きです。でも、熱心には聞いてきませんでした。それは、どうしてか。自問自答してもよくわかりません。要は、タイミングなのです。 kumac がジャズをあまり聴かない時期にデビューし、話題となって
気になっていたら、たちまち引退してしまい。結局、CDでしか彼女の演奏は聴けないことになってしまいました。過去のミュージシャンや海外のミュージシャンの場合、生演奏をきけなくてもいいのですが、日本に住んでいるミュージシャンの場合、一度はこの体で体験したということがあり、それが無理な場合は、自然と距離が生まれます。なので、大西順子の場合、視野にないのです。
ところが、kumac の住む田舎町に今度、現れるらしいのです。それも、日野皓正と綾戸智恵というメンツで、ちょっと意表を突くメンツです。てなわけで、この復帰作を買った次第です。
冒頭、1曲目、「Tea Time 2」の出だしの音は、完全に菊地成孔の世界、と思わせるところがあります。それは、軽妙で無機質な音なのですが、そこに大西順子の重厚なピアノの響きが重なってくるという演奏です。互いの共通項は、じめじめしていなくて乾いているということです。ここでの、大西順子の演奏は、自己の世界を追い詰めるということではなく、菊地成孔の提示する音に従順です。大西順子のジャズに対する姿勢は、<破壊>という言葉で括ることができそうな気がしていますが、それが引退という行動に繋がるのかなと思のですけれど、ここでは、新鮮な気持で活き活きと弾くことができるという、そういう状態を大西順子にもたらしていることで、この作品は成功しているのだろうと思います。でも、どうもこれに飽きたら、つまり外来因子の刺激だけで泳ぎ回れるほど、ストイックな姿勢を持って音楽に対峙する場合は、甘くはないのではなかろうかと思います。
ざっと、聴いての最終的な kumac の感想はこのようなものです。あとは、大西順子の既存の世界を純粋に楽しむということで良いのだと思います。それなりに、プロデュサーが明確な位置を占め、音楽全体を文字通り統括しているのですから、色鮮やかではあるし、一曲ごとに明確な想像へのこだわり、あるいは煽りはあるのであると思います。
人に気に入れらることに淡泊な人がいます。大西順子もその一人だと思います。ジャズミュージシャンは、そういう人の存在の締める割合が大きな職種だと思うのですが。例えば、レニー・トリスターノもそういう部類だろうし、マイルス・デイビスもそれに近いと思います。では何のためにプロとなって演奏の機会を得ようとするのか、そして何のために求めに応じるのかとなるのですが。それは、性(さが)なのだろうと思います。ざっくりとした話で恐縮です・・・。だから、定まりがない。人のために生きようとしない、そんな姿勢を大西順子には感じます。
結局、菊地成孔の存在は、使い勝手の良い、使い捨てコンロのようなものかもしれません。菊地成孔は、流行に敏感だと思います。時代の模倣に徹しています、創っているようで実は追随しているというのが私の印象です。自己の音楽の形成においては、まだ慣れてない。器用ではないと思います。その理由は、音が明らかに時代の雰囲気に対して類似性を有しているからです。
だから、菊地成孔はここでは完全に大西順子に喰われていると思ってしまいます。
John Lewis『Evolution』
ジョン・ルイスのことを書こうとして、MJQのことから始めてしまう、ありきたいりな導入をしてしまっているけど、ラストコンサートの良さを列挙しましたが、kumac は、その良さを際立たせる大事な要素があると思っています。それは、室内楽だから、ということです。多くのジャズの演奏は、コンサートホールやライブハウスなど室内で演奏されるので、室内楽というのは当然、と考えますが、kumac が際立つ要素として取り上げた<室内楽>は、<制約>といってもいいかもしれません。例えば、俳句や短歌のように、定型のある文学のことを想像していただければ、なんとなく分かるかも知れません。その制約、俳句で言えば、季語や五・七・五の文字の制限などです。俳句でも自由律俳句や無季語の俳句がありますが、そしてそれを否定することはないと思っていますし、自由律俳句の中にも素晴らしい作品があります。
これ以上書いて行くと、本題から限りなく外れるので、ここいらでこのジョン・ルイスの作品『Evolution』に戻ります。まあ、ジャケ買いですね。というのは、ジョン・ルイスの作品をこれまで幾つか買いましたが、さほどに良いと思ったものはありませんでした。なので、今回、きのCDをどうして買ったのかという説明は、ジャケ買い以外の動機はないということになります。それと、若干、ソロピアノ集(それも、「クラシック」という言葉がどこにも見当たらなかったことも、今思えば、買っても良いかなと思った理由かも知れません。)ということも食指が動いた理由の一つです。
結果、素晴らしい作品です。ジョン・ルイスのジャズに対する前向きなアプローチが聴くことができます。有名なスタンダードナンバーが多く収められていますが、その曲の解釈も面白いです。例えば6曲目の「Django」は、流れるような旋律をわざとぶった切って、曲の持つ緊張感を、裏の裏をかいて、消しています。ほとんどの人は、どんなメロディーか知って聴くはずです。次に、どんな旋律が流れてくるか分かっているはずです、だから小細工の使用がないところを、旋律の流れを切ることで、聴く人の先入観を裏切って、次への期待を持たせます。その時点でも、もう曲本来の持つあのメロディーの密度の濃淡を違う方向から光を浴びせ、違う色彩に変えています。そんなに大胆に変わる訳ではないです。曲のメロディーから外れるようなことはしませんから、だからこそ面白いとも言えます。その後の曲の展開も、MJQからの演奏に通じる手法を持ちながら、ジョン・ルイスの個性で全体を覆う作品に仕上げています。
そんな感じで、どの曲もとても楽しめました。
あとは、ジョン・ルイスの呻き声が聞こえるところが最高ですね。
エヴォリューション/ワーナーミュージック・ジャパン

¥1,028
Amazon.co.jp
にほんブログ村
Ray Brown『This Is Ray Brown』
2曲目「Upstairs Blues」は、レイ・ブラウンのソロベースによるテーマの提示から始まるブルース曲。その揺りかごのような眠りを誘うリズムの中を、フルート、ベースのソロが続く、どこかチャーリー・ミンガスを思わせるレイ・ブラウンの演奏は、似ているということではなく、渾身の気持ちを込めてベースをかき鳴らすという行為自体が、とても激しさを持っているということではないかと思わせます。楽器として、とても地味ですが、それが一旦、心に響いてくると、激しく揺さぶられる。アフリカン・アメリカンの悲哀をここでは強く感じます。そういう意味で、ミンガスと同じ意識をベースという楽器に持っていたのではないでしょうか。最終的な音楽としての表現方法は違っていても、素は同じだと思わせます。
3曲目「Indiana (Back Hpme Again In)は、テーマをレイ・ブラウンが弾く、テーマを引くと行っても主旋律を高音域で奏でるということはせずに、あくまでべーシングスタイルを守ってています。つまり、低音域をカバーする本来の役目を果たしつつ、テーマを受け持つということで、変に自分のスタイルを曲げてまで自己主張をしようとしない姿勢に清さを感じます。アップテンポの曲で、後半のオスカー・ピーターソンの早弾きに対するレイ・ブラウンのウォーキングベースが見事です。
5曲目「Tak The 'A' Train」で、初めて伴奏に徹していたハーブ・エリスがソロをとります。泣きの入るブルージーなギターが面白いです。
6曲目「Cool Walk」は、この作品の中で白眉の演奏です。レイ・ブラウンのフォービートのウォーキングベースでテーマが始まり、ハーブ・エリスがリズムギターを弾き鳴らし、オスカー・ピーターソンがオルガンの様々な音色でおもしろおかしくバッキングをします。その中を、レイ・ブラウンがソロをとってゆきます。それに呼応するオスカー・ピーターソン。ハーブ・エリスがソロをとるときには、レイ・ブラウンはウォーキングベースに徹します。その表情あるリズムの受け渡しが見事です。というか、楽しいです。
レイ・ブラウンとは、けっして饒舌ではなく、出しゃばらす、低音域を黙々と動き回るベース奏者でることを強く自己主張した作品です。
ディス・イズ・レイ・ブラウン/ポリドール

¥1,888
Amazon.co.jp
にほんブログ村
Sal Mosca & Warne Marsh『Quartet volume 1』
この二人の共演はかなり多いようです。有名なところでは、『リー・コニッツ・ウィズ・ウォーン・マーシュ』でピアノを演奏しています。トリスターノ派の音楽理論が染みついている二人なので、そのような演奏になっています。どこがどうのと kumac が書けないのは、イマイチ、トリスターノ派の音楽が理解できていないからです。でも、こうやって結構、飽きずに聴いているのは、好きだからです。どういうとこがと、聞かれたら、「よくわからないところ、と、でも、妙に(気持ちに)引っかかってくるところがあるから」という感じの答えになるのかなと思います。
やる気度でいえば、サル・モスカが断然、ここではやる気を出しています。この日のギグは、もしかして、サル・モスカの名前でクレジットされていたのかもしれません。ウォーン・マーシュの出番は、それ相応にありますが、さして気持ちが入った演奏でもなく、要はいつものウォーン・マーシュらしさ満開で、果敢に何かに挑戦する気配は皆無です。それにくらべ、サル・モスカは師、トリスターノの演奏をさらに進化させようとする気迫が演奏に感じられます。具体的に言えば、リズムのずらしを次への推進力に変えている、ということでしょうか。ピアノは、メロディアンスな打楽器なので、リズムにメリハリを加えずに、一定にしてメロディーだけで音楽を家具(サティとは違うのですが)や筆記用具のようにさりげなく使う、仕舞う。そいういう生活様式に対して、本棚を道具箱のように使うとか、椅子を逆さに天井から吊し、部屋のディスプレイにするとか、なんかそんな気持ちを感じます。
そういう風に考えてゆくと、5曲目「Dig - Doll」ののっけから畳み掛けてくるウォーン・マーシュのテナーのグネグネ感が最高に緊張感をもたらしてくれます。しかし、興が乗ったところで、何故かこの演奏はウォーン・マーシュのソロの途中でフェードカットされています。この後、続くマーシュのソロがなにか破綻をもたらしたのでしょうか。6曲目「Under - Bach」でも、マーシュの独壇場となっています。いいですね。ここでの演奏は、最高です。やる気を出しているな。前言撤回です。
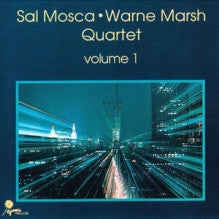
にほんブログ村
Lorenzo Tucci『Sparkle』
kumacは、ファブリッツオ・ボッソとブルーノート東京でライブをしたときに聴きぱぐっているので、実際の生の演奏は聴いていないわけで、その意味ではかなり我田引水になりますが、きちんと自己主張ができるドラマーとしては、今、名前を挙げろと言われれば、外せないのではないかと思います。
このリーダー作では、ピアノの Luca Mannutza が音の作りでは前面に出ているのですが、ソロの時点ではあまりリーダーシップを取ってはいません。そういうことでいえば、トータルな面でロレンツォ・ツォッチのやりたい音楽が表現されている(リーダー作だから当然なのですが)と思います。例えば、ボッソとやった作品などは、互いに自己主張しながらその場の即興的な部分で、新鮮な音楽を作り上げてゆくわけですが、そういうところはあまりないのではないかと思います。
では、ロレンツォ・ツォッチはどのような音楽を指向しているのかと考えれば、アーバン(都会的)な音なのかなとこの時点では思います。Flavio Boltni のトランペットにしても、ソフトな音色です。そのフレーズも、どちらかといえばエモーショナルではなく、洗練された情感を込めたものです。このへんで、狙っている音楽が見えてくる印象があります。全10曲中7曲がロレンツォ・ツォッチのオリジナルです。
かといって、昔のブライアン・ブレイドのフェローシップのような明確なコンセプトを持っているわけではなく、あくまでジャズ本来のもつ即興性(イコール、ドラミングの妙みたいなところです)にこだわっていると思います。まあ、印象によっては、中途半端という感じを持つかも知れません。物足りなさなを感じたら、それは聴くタイミングを外したと思うしかないのではと思います。
7曲目「Two Years」でのロレンツォ・ツォッチの息を切らさない、手数の多いドラミングは圧巻です。肝心なとこころに強弱のある衝撃派を入れ込み、推進力を作ってゆきます。これは、最高にいいですね。思わず聞き惚れるドラミングです。このメンバーは、若手主体なのだと思いますが、これが一癖二癖ある強者であれば、かなりの高見まで演奏は舞い上がるのではないかと思います。
最後に、ピアニストはエンリコ・ピエラヌンツィの影響をなにがしか受けているような気がします。音が近いです。タッチと言い、音の選び方と言い、間といい。8曲目スティングの「Seven Days」での演奏は、まさにそういう印象です。ですから、気持ちよい、アメリカのブルージーな音色が混じる音ではなく、純粋なクラシカル的なアプローチのジャズピアノです。
最後の最後、最後の曲「E po' Cha fa」のKarimaのボーカルはいいですね。新緑季節にもってこいです。なんか、さわやかな気分になりました。
Sparkle/VIA VENETO JAZZ

¥2,369
Amazon.co.jp
にほんブログ村
Sonny Clark『My Conception』
確かに、kumac がソニー・クラークを沢山聞いていた時期は、、まだCDがなかった時期で、CD全盛の時代になる直前にLPはほとんどすべて処分したので、昔買ったことのあるLPをわざわざCDで買わなくてもいいやという、ある種、ジャズに対する禁欲的(?)で誠実(?)な態度(?)を押し通してきたわけです。
そして、この期に及んでも、長らく未発表だった『My Conception』を聴いているわけです。
ソニ・クラークは禁欲的なピアニストである。それ故、アメリカでは人気を得られなかった(巷から聞こえてくる話であり、本当に人気がなかったのか、kumac は真実は知らない。)のではないかと思っています。演奏の、どこかでエモーショナルになる部分が出てきても良いのですが、その盛り上がりがないのです。ただ単に自己に対してブルージーでソウルフルであるだけで、視聴者を喜ばせようとする意識が感じられなません。
多分、日本人とは、そういう点で気が合ったのではないでしょうか。こう聴いていると、ドナルド・バードやハンク・モブレーのホーン楽器の華やかさ微塵も感じらません。例えば、3曲目「Minor Meeting」ですが、激しくブローするバードとモブレーの次に現れるソニー・クラークのソロは、なんとも地味です。どう考えても、内に向いている演奏です。じっと目を瞑って、一音一音をかみしめて聴いてゆけば、思わずほくそ笑んでしまうソニー・クラークの演奏があるのですが、そういう精神感覚でアメリカの人達が聴くとはとても想像できないのです。
いや、中には例外もあり、虚無僧の格好をしてマンハッタンを闊歩するアメリカ人もいるはずで、人気が全くなかったわけではないと思います。
アート・ブレイキーの煽るファンキーなドラミングに対して、あくまでクールな態度で音を響かせるソニー・クラークって面白いです。
My Conception (Remastered) [Bonus Track Version]/Lilith Records

¥価格不明
Amazon.co.jp
にほんブログ村
Andrea Cali『Take The Line』
冒頭「Why Are You Looking At Me ?」は、直訳すれば「あなたは、どうしてわたしを見ているの」となるわけで、それは冒頭に書いた写真が物語る謎かけのようなものなのかもしれません。意訳すれば、「わたしの音楽はどうでしたか」と問いかけているような気もします。この「Why Are You Looking At Me ?」は、彼、Andrea Cali の最も聞いて欲しい曲ということになれば、<異才を放つ>と言ってもいいかもしれません。そう、ダリとカリの関係です。
どうしてかと言えば、その抽象的かつ耽美的かつ攻撃的な音とピアノのタッチは、かつてあまり聴いたことのない(kumac の狭い知識で言えば、「イタリアのピアニストとして」は、です。)ものだからです。どこかブルジーでもあるし、セシル・テーラー的な音のパズルの組み合わせといった音の匂いもするし、ロマンチックではないけれど乾いた情感がある、ちょっと不思議な演奏です。一番に似合う表現で言えば、「小気味よい」ということかなと思います。この表現は、かつてヨーロッパのピアニストには、あまり感じなかった感覚です。
その流れは2曲目「lennie's Pennier」にも引き継がれます。曲名の通り、レニー・トリスターノの曲です。始まりは、コニッツの「モーション」を彷彿させるベースの無機質で整然としたビートが効いた冷淡で情熱的な演奏を聴かせてくれます。面白いです。全体的には、トリスターノをなぞった、ということなのだと思います。
で、最初の2曲まででしょうか。鬼才らしき言葉をかけても良いと思うのは、次の曲からは、ああヨーロッパのピアニストだと確信を持たせるクラシカルなそして情緒的な演奏に入ります。3曲目「Ultina Piggia」はエンリコ・ピエラヌンツィを思い出させる曲調です。
が、ここでこのアルバムのコンセプトが理解できたような気がします。それは、全8曲の曲の並びが、オリジナル→他人(歴史に名を残しているジャズミュージシャン、あるいはスタンダード)の曲、という並びになっているのです。そして、オリジナルは、次の曲に対する Andrea Cali の挑戦(俺だったら、こういう演奏をするが、どうだい?)という理解が可能なのです。ですから、音楽性で言えば、ややもするとカメレオン的な捉えどころの無いものとなっている(曲によってイメージが変わる)のです。他人の曲自体、彼が演奏して表現しているので、個性が強く出ている作品であることに違いはありません。
ですから、3曲目のエンリコ・ピエラヌンツィ的情緒は、スタンダード曲の4曲目「If I Should Lose You」に照応し、5曲目の「Let Be」は、6曲目のビル・エバンスの「Five」に照応するわけです。7曲目は、オリジナル、そして8曲目はそれに照応するチック・コリアの曲です。
そうやって勝手に解釈して聴くと、とても面白いです。
この後の、Andrea Cali の成長を見続けたくなりますね。いやあ、本当に面白いです。

にほんブログ村
Halperin-Hyberg Connection『Snow Tiger』
CDのジャケットのミュージシャンの集合写真を見る限り、ジミー・ハルペイン以外はみんな30歳前後の若いミュージシャンです。とにかく、あまり情報がありません。
実際の音の中身は、ジミー・ハルペインのテナーを前面に押し出した演奏が全篇続きます。最初に、レニー・トリスターノに師事したと書きましたが、まさしく演奏はトリスターノ派のそのものです。その証拠に、収録されている全11曲中、トリスターノの曲が3曲、コニッツの曲が2曲、ウォーン・マーシュの曲が1曲あります。そして、他にジミー・ハルペインの曲が2曲ありますが、それ自体トリスターノ派の流れを汲んだメロディー感覚に淀みない無機物感を持ったものです。まったくもって、冷蔵の蒼白の世界がそこに展開されています。
トリスターノ、コニッツやマーシュが好きな方にとっては、涎が垂れてくる感激の作品です。ということは、kumac にとってはとても心地よい至上の音楽ということです。こんな雪の降り積もる冷え冷えとした土曜の朝に、このヒンヤリする肌触りを持つ音を聴かせられる、それも新しい録音として、聴けるのは、とてもぞくぞくして、鳥肌が立ちます。とても、嬉しいです。
面白いのは、リーダーとおぼしき、ギターの Pal Nyberg が作曲した曲が1曲ほど入っているのですが、それが他の癖のある曲と違和感なく溶け合っているのはもちろんですが、しかし、明らかに異質な曲です。
メロディーラインが甘くて、明瞭で、歯切れに良い作品です。それだけで、違いが一目瞭然、分かるのですが、この曲は他の曲と違って、ソロは Pal Nyberg が最初に取ります。そして、ベースのソロが入り、ジミー・ハルペインが締めます。とても、美しい曲です。北欧らしい、透き通った音の伸びが放物線を綺麗に描いています。どうして、この曲を入れたのか、うがった見方ですが、 Pal Nyberg がこの曲に「Siri」という題名を付けています。これは kumac の思い込みかも知れませんが、Appleの iOS に入っている人工知能もどきの音声サービス Siri と関連性があるのではないでしょうか。
つまり、「なにか、トリスターノの曲を演奏してみて」と、Siri にお願いしたら、こんな曲になったという現代的な解釈といっていいのかなと思います。この演奏から察するに、Pal Nyberg は、トリスターノ派の演奏を主体としている訳ではなく、いろんな可能性を秘めた奏者ということだと思います。だから、彼の他の作品では、また違う面を聴くことができると思います。
それはさておき、最高の演奏は9曲目トリスターノの曲「Leave me」です。これは、言い切ります。とてもパッセージの速い曲です。そして、切れ味が鋭いどいです。ちょっと触れただけで、皮膚が切れて、血が噴き出しそうなスリル感。緊張感があります。
そして、テナーのジミー・ハルペインの演奏の白眉は、10曲目「Subatomic Dominant」ではないでしょうか。これ、彼のオリジナル曲です。思う存分、テナーを吹いています。ジミー・ハルペインは、コニッツの自由さとマーシュの窮屈さのちょうど中間でしょうか、中間と書くとどっか中途半端という印象を持たれますが、そうではなく誰にも似ていないし、強いて喩えるならば、トリスターノ派から派生してドルフィーに近い演奏スタイルを確立しているということです。
最後に、ギターの Pal Nyberg の演奏について、触れておきたいと思います。11曲目のボーナストラックと表記されているスタンダードナンバーの「How Deep Is The Ocean」の演奏を聴くと、オーソドックスなシングルトーンホーンライクな演奏をしてくれるギター奏者です。どこか、間延びしたギター奏者が多い北欧のジャズ。ギタリストとはちょっと一線を画すかもしれません。ヨーロピアンジャズの指向というよりうは、かなりジャズのメインストリームを押さえたスタイルを持っています。とても、好感が持てます。
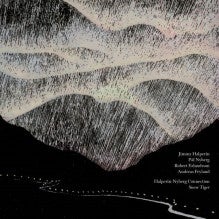
にほんブログ村
Hans Olding『Projeto Brasil!』
作品のコンセプトは、表題のとおりブラジル音楽へのオマージュ的なものです。冒頭、1曲目「Tom」は、最初に入ってきた音を聴いたときに、一瞬、チック・コリアのリターンフォーエバーを彷彿とさせたのですが、チェロの音が入ってきて、またギターのどこかテリエ・リピダルを彷彿とさせる無機質な響きが、直ぐにその印象を消し去ります。
ブラジル音楽に近似してゆこうとする姿勢なので、明るい、軽快なボサノヴァの音かと思えば、まったく違います。リズミカルでもないですし、そのミスマッチが、どうにもこうにも朝から考えさせられてしまします。「深淵」かつ「クラシカル」かつ「メランコリック」なのです。この三つの言葉からとてもブラジル音楽は想像できません。ただし、ゆったりとしたメロディーは、まさしくラテンの音色で染め尽くされています。
つまり、ブラジル音楽が好きな Hans Olding が、自分なりのブラジル音楽、特にメロディーに感化された音楽を作ったと言うことではないでしょうか。あの、太陽の燦々と注ぐ、砂浜で尻の肉剥き出しにビキニ姿で闊歩する若い女性のが、その後、家に帰って、喜怒哀楽を一人鏡に向かって自問自答する、そんな内気な青春を音楽で表現したものなのかもしれません。
凄いなと思ったのは、アントニオ・カルロス・ジョビンの曲が全9曲中5曲入っているのですが、どれも、前述したようにメランコリーな演奏にも関わらず、メロディーの美しさが際だって響いてきます。多分、ジョビンの曲が素晴らしいからだと思います(多分に聞き慣れていたこともあるからかもしれませんが)。なんと言っていいのか、不思議な世界だし、ちょっと抽象化した美を見せられたような感覚です。
ブラジルという表題に惑わされて買った(私は違いますが)ら、大失敗です(後半の曲は、けっこう軽快なノリです)。チェロとフルートは完全にジャズのアプローチはしていません、クラシックのスタンスを貫いています。しかし、なんかどこか微笑ましい、外では容器ですが、家で内気な人間を見ているようです。

にほんブログ村
Domenico Sanna『Brooklyn Beat!』
タイトルの通り、この作品の肝はビート、つまりリズムにあります。終始一貫して、強烈に襲いかかるのはドラマーの Dana Hwkins のキレのあるドラミングです。ドスがきいているわけでもなく、ソウルフルな心地良さを感じさせるわけでもなく、とにかく手数が多い印象です。さりとて、音に直線的で、あっさりとしてストレートな印象があります。結局、切れがいいね、となるのですが、このリズムの感覚は、なかなか滅多にお目にかかれない産物です。トニー・ウイリアムスとも違う、バリー・アルトシェルとも違う新鮮な感覚を持ちました。
またベースの Ameen Saleem は、逆に重厚な音を響かせます。バスドラムをかき消すようなベースのビートです。このへんの三者のバランスは見事かなと思います。
で、主人公の Domenico Sanna ですが、この作品ではアコーステックと電子ピアノを使い分けています。でも、あまり両者で演奏や聴いた音に違いはないですね。乗りの良いピアノでは決してないです。一音、一音自分の間で演奏をします。だから、ドラムとベースの強烈なビートに対して、直接的な反応ではなく、意識的に距離を置いた演奏をしています。それが、彼の間なのだと思うのですが、心地よい印象は持ちます。そして、ただピアノをリズムに乗せて鳴らせば良いというアプローチはしていません。
つまり、今風のロックの影響をモロに感じさせるジャズにはなっていないということです。これは、珍しいのかなと思ったりもします。どちらかといいえば、フリーフォームに近い演奏ですが、しかし、誰も彼らの音楽を聴いて、フリージャズの系譜としては考えないでしょう。
内面的な印象画風な演奏です。6曲目のスタンダードナンバーの「Body And Soul」なんかを聴けば、そのことは良く理解できると思います。表面的には原曲の印象は消え失せています。再度構築し直すと言うよりも、既に原曲の良さが血肉になった上で、綺麗に排泄している印象です。すばらしい、リリシズムです。こういう音を、じっくりと聞いていると、嬉しくなりますね。
Brooklyn Beat!/Imports

¥2,553
Amazon.co.jp
にほんブログ村